- 2025.07.07
- 社長ブログ
【連載】横浜植木株式会社 – 社長インタビュー第2回
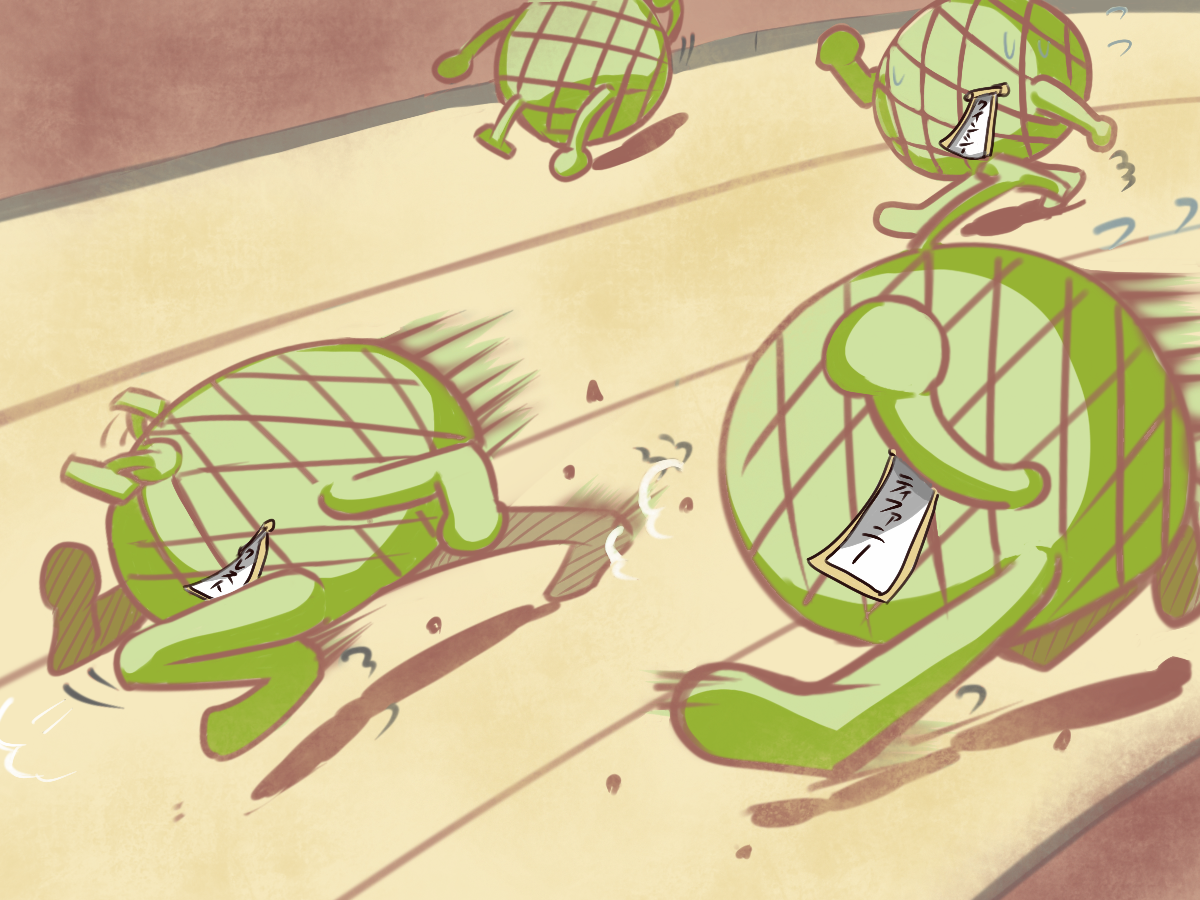
横浜植木株式会社は、種子の開発・生産・販売や植栽などを手がける老舗企業です。今回は当社の社長にインタビューを行い、幼少期から現在に至るまでの軌跡や、メロンやピーマンなど数々の品種開発秘話についてお話を伺った連載インタビューの第2回です。
前回のインタビューはこちらからお読みいただけます。
横浜植木での挑戦——メロン育種への道
-インタビュアー
学生時代を経て、横浜植木にはどのようなきっかけで入社されたのですか?
-社長
横浜植木には1981年に入社しました。大学時代は遺伝育種学の研究室に所属していて、遺伝とか品種改良にとても興味を持っていたんです。それと加えて、私は農家の長男でしたので、実家に戻ることが親の暗黙の了解のようになっていました。そんな背景もあって、「実家から通える場所で、しかも育種ができる会社」として、横浜植木が最有力候補になったんです。ただ、入社して最初は驚きました。事務所はまるで工事現場にあるような仮設小屋のようで、職員が3名ほど、農場の作業員も数名という小規模な体制でした。学生時代に思い描いていた会社員生活とは、正直、かなりギャップがありましたね。

-インタビュアー
入社されたときは、すぐに品種改良の仕事に携わることができたのですか?
-社長
いいえ、最初からすぐに品種改良に関われたわけではありません。入社後は本社の寮に住みながら、本社内での発送加工の研修からスタートしました。特に印象に残っているのは、メロンの種を袋詰めする作業です。毎日のように、手作業で種を数えては袋に詰めていました。当時はまだ自動の袋詰め機などはなく、100粒を一粒ずつ手で数えて詰める、非常に地道な作業でした。今思い返すと、気が遠くなるような作業でしたが、ものづくりの基本や、作物に対する丁寧な向き合い方を学んだ時間でもありました。
-インタビュアー
100粒ずつ手作業で数えるなんて、本当に気の遠くなる作業ですね。本格的な育種に携わるようになったのはいつ頃からですか?
-社長
本社研修を終えた後、農場に配属されメロンを担当することになりました。ただ、上司はメロンの普及活動でほとんど農場にいなかったので、現場の仕事は作業員のおばちゃんたちに教わりながら覚えました。そういった状況もあって、比較的早い段階で育種を任せてもらえるようになったんです。
最初に取り組んだのは、当社にはなかった「つる割れ病抵抗性」の育種でした。菌の培養などは全くの未経験でしたが、社内に有る資材を使い、見よう見まねでなんとか取り組みました。 また、同時期に並行して開発していたのが赤肉メロンです。実は、入社するまでメロンを見ることも食べることもほとんどなかった私にとって、赤肉メロンはとても新鮮で強く興味を引きました。
-インタビュアー
わずか入社2、3年目で品種開発を任されるとは、大変な挑戦だったでしょうね。新人時代に苦労されたことや、印象に残っているエピソードはありますか?
-社長
そうですね、振り返ると無謀な挑戦だったかもしれません。私が入社した頃、日本経済は急成長し、バブル期に向かっていました。それに伴い、日本各地でメロンの産地も急速に拡大していきました。上司は産地の普及活動に追われ、育種に時間を割く余裕がなかったため、経験のない私にその業務が丸投げされる形となりました。当時は不安でしたが、今思えば「若いうちにチャンスをもらえた」と感謝しています。自分なりに試行錯誤しながら挑戦させてもらえたことが、その後の成長につながったと思います。
結果として、入社6年目にはいくつもの品種を試作できるようになりました。たとえば、つる割れ病抵抗性を持つアールスメロン「クレスト」、立体栽培向け赤肉メロン「ティファニー」、地這栽培向け赤肉メロン「クインシー」、さらに極早生・地這栽培向けの「サンデーレッド」などです。これらは、私にとっても非常に思い入れのある品種達です。
メロン品種開発と常識への挑戦
-インタビュアー
若いうちに大きな仕事を任せてもらえるというのは、本当に貴重な経験ですね。メロンの品種開発において、どのようなことにこだわられていたんでしょうか?
-社長
そうですね、品種開発では、長所と短所が表裏一体であることが多く、メロンにおいても同様でした。香りがあり、肉質の柔らかい品種は日持ちが悪く、逆に日持ちの良い品種は香りが乏しく、硬くて美味しくないのが常識でした。この常識を覆したい一心で、肉質が柔らかく、なおかつ日持ちの良いメロンの開発に懸命に取り組みました。そして誕生したのが、現在のメロンの品種達です。品種開発とは、常識を覆すことだと実感した瞬間でした。

-インタビュアー
「常識を覆す」というのは、まさに革新の本質ですね。でも、赤肉メロンの開発には苦労があったと聞いています。当時は受け入れられなかったのでしょうか?
-社長
そうですね。おっしゃる通り、当時は赤肉メロン自体がほとんど普及していませんでした。思いを込めて育成した赤肉メロンを、農協や試験場、市場など、プロの方々が集まる場へ期待を込めて持ち込み、試食会を行いました。
しかし、返ってきた反応は厳しものでした。「カボチャのようで食欲が湧かない」とか、「メロンらしくない」といった、否定的な声が多く寄せられました。そんなとき、小さかった姪に試しに食べさせたところ、「きれい!美味しい!」と目を輝かせて喜んで食べてくれたんです。その姿を見た瞬間、不思議とやる気が戻って来たんですよ、子供の先入観がない素直な反応が、あの時の私の背中をそっと押してくれたんだと思います。
-インタビュアー
素敵なエピソードですね。子どもの素直な反応って本当に価値がありますよね。赤肉メロンが普及していく過程はどのようなものでしたか?徐々に市場に受け入れられていったのでしょうか?
-社長
ありがとうございます。当時の日本では、赤肉メロンがほとんど流通していませんでした。過去に上司が開発した「ルビーメロン」は、香りがよく美味しかったのですが、日持ちが悪く糖度ものりにくかったため、残念ながら市場には定着しませんでした。
そうした中、昭和60年代頃から夕張メロンの知名度が全国的に高まり、それに伴って赤肉メロンへの関心も少しずつ高まっていきました。そうしたタイミングで、高糖度で日持ちに優れた「クインシーメロン」が登場し、大きな注目を集めました。 さらに、市場や産地のニーズに合わせた品種を発表しました、たとえば、東北や北海道など雪解け後の限られた期間でも栽培が可能な超極早生品種「サンデーレッド」、赤肉でありながらアールスメロンのようにアンテナ付きで出荷できる「ティファニー」など、さまざまな特色を持つ品種が次々に登場してきました。
-インタビュアー
市場のニーズに合わせて、様々な品種を開発されていたのですね。赤肉メロンが市場に受け入れられるようになったきっかけとなる出来事などもあったのでしょうか?
-社長
はい、ありました。最初に「クインシーメロン」を栽培してくださったのは、茨城県の生産者さんでした。その方は、春メロンの後に当社のアールスメロンを作っていてくれた方で、私が「ちょっと変わったメロンを開発したんです」とお話ししたところ、「ぜひ栽培してみたい」と快く引き受けてくれたんです。こうして、クインシーメロンが世に出ることになりました。
当時としては珍しい赤肉メロンで、夕張メロンの知名度も高まっていたことも追い風となり、なんと1ケース1万円以上の高値がついたんです。それが話題を呼び、市場やスーパー、産地にも一気に広がっていきました。 特にクインシーメロンは、果肉が柔らかいのにしっかりしていて肉崩れしにくく、糖度が非常に高い。しかも「ハズレがない」と評判となり、カットメロンの需要拡大にもつながりました。いわば、カットメロンの火付け役になった存在だと思います。
-インタビュアー
そんな冒険的な試みがあったんですね!メロン販売の売上が成長する過程で、どのような影響や変化があったのでしょうか?
-社長
はい、平成に入ると全国的にメロンの産地がどんどん拡大していきました。特に熊本では、秋作のアールスメロンだけで栽培面積が1,000ヘクタールに達し、春メロンを含めると3,000ヘクタールを超える規模になりました。
当時、私は20代後半から30代の若手でしたが、栽培講習会や圃場巡回などで全国を飛び回るようになりました。産地では「先生」と呼ばれることもありましたが、実際には私の方が生産者の皆さんから多くを学ばさせていただいたと感じています。
また、農場には全国の農協や生産部会からの視察が相次ぎ、対応に追われる毎日でした。さらに、全国各地のメロン産地から、若手の農協職員や生産者のご子息といった研修生も受け入れており、農場は常ににぎやかで活気に満ちていました。こうした平成の時代を通じて、横浜植木で研修を受けた人材が、今では全国各地の産地で活躍しています。 品種開発の面でも進化してきました。平成5年には、「クレスト」の後継品種として「雅(みやび)」を発売。また、赤肉アールス系の「ティファニー」の後継品種として「妃(きさき)」を発表し、これらの品種がアールス系市場のシェア拡大に大きく貢献しました。
-インタビュアー
20代で「先生」と呼ばれていたなんて、すごいですね!品質管理も大切だったと思いますが、種子の品質管理にも取り組まれたそうですね?
-社長
私が入社した昭和50年代は、ちょうどアールスメロンの地床栽培が広がり始めた時期でした。当時、アールスメロンは静岡県や千葉県などの限られた地域の、特別な温室でしか栽培できない高級フルーツとされていたんです。
その特別な温室とは、「スリークォーター」と呼ばれるガラス温室で、金網ベッドの上に土を乗せて栽培するスタイルです。水分管理や温度湿度管理が非常に繊細で高度な技術が求められていました。そうした中で、もっと手軽に栽培できるように、ビニールハウスでの土耕栽培に対応した品種と技術を開発し、全国へ広めたのが横浜植木でした。水分管理が難しい土耕でも安定して果実にネットが入り、糖度も乗るような品種と、それに適した栽培技術を確立したのです。
私の先輩である高島さんは、その普及活動に尽力され、「ウエキ式アールスメロン栽培技術」を、多くの産地で当たり前に使われる技術へと育て上げました。
種子の品質管理において大きな転機となったのは、「クレスト」の試作時です。当時、当社では薬剤による種子消毒を行っていましたが、試作圃場でウイルスと見られる症状が発生し、一部の産地からは「種子が発生源ではないか」とのお声をいただきました。このため、状況の丁寧な説明と信頼回復に努める必要がありました。
当時は、まだ社内にウイルス検査の十分な技術が整っていなかったため、全国の研究機関を訪ね、適切な検査法の導入を模索しました。その結果、信頼性の高い検査法を確立し、産地からの信頼に応えるとともに、種子消毒もより効果的な方法に全面的に切り替えることができました。こうして、これまで以上に健全な種子の供給体制を整えることができたのです。
以降、同様のウイルス問題は一切発生せず、「クレスト」は一気に普及しました。この経験を通じて、問題が起きたときこそ逃げずに正面から向き合い、真剣に取り組むことで、かえって大きなチャンスにつながるのだと学びました。
-インタビュアー
ピンチを新たな体制強化のキッカケに変えられたのですね。メロン以外にも担当された品目があったと伺っていますが、その際に注意されていた事はありますか?
-社長
はい。農場では主に、メロン、ピーマン・パプリカ、そしてダイコンの3品目の開発を担当してきました。それぞれの作物について、現在は後任の育種担当者たちがしっかりと開発を引き継いでくれています。
当社は、取り扱う品目が多くないため、通常は一人のブリーダーが一つの品目を長年にわたって担当するのが基本です。ただ、それでは新品目の開発が進まず、若手ブリーダーの成長機会も限られてしまうと感じていました。ですから私は、後任が育ったタイミングで自分は早めに身を引き、次の人にバトンを渡すことを意識してきました。もちろん、口を出したくなることや心配なことはたくさんありましたが、そこを我慢できるかどうかが、後輩を育てられるかどうかの分かれ道だと思っています。そのためにも、自分の関心を次の品目に向けることで、自然と気持ちの切り替えができるようにしていました。
とはいえ、「新たな品目に取り組む」という考えを他のブリーダーに理解してもらうのは簡単ではありませんでした。なぜなら、新しい品目を始めるということは、これまで培ってきたスキルや信頼を一度手放し、ゼロからスタートするということだからです。ただ、私自身はあまり過去の実績に執着するタイプではなく、どちらかというと新しいことへの興味が強い方でした。だからこそ、未知の分野に飛び込むことにも前向きに取り組めたのだと思います。
-インタビュアー
新たな挑戦を受け入れる柔軟性も素晴らしいですね。その後は、ピーマンの育種にも取り組まれたそうですね。これはどのようなきっかけだったのでしょうか?
その気になる続きは、ぜひ「横浜植木株式会社 – 連載社長インタビュー第3回」で!!
社長ブログ読者の皆様からの伊藤社長へのご質問やご相談を受け付けています。